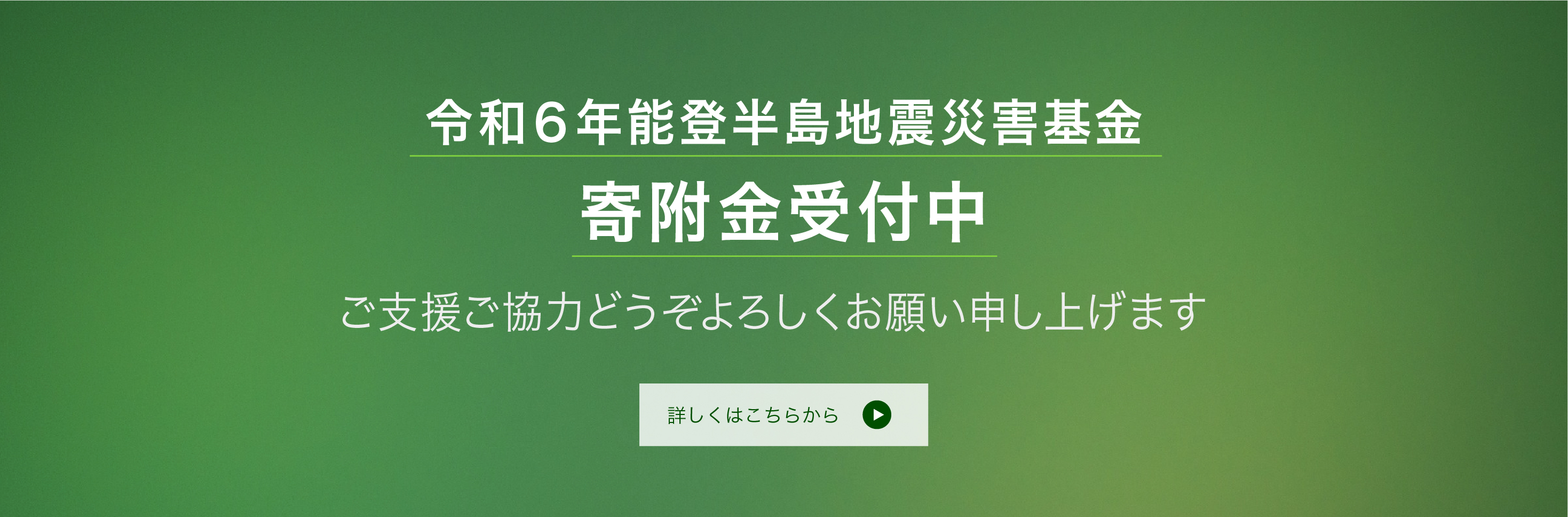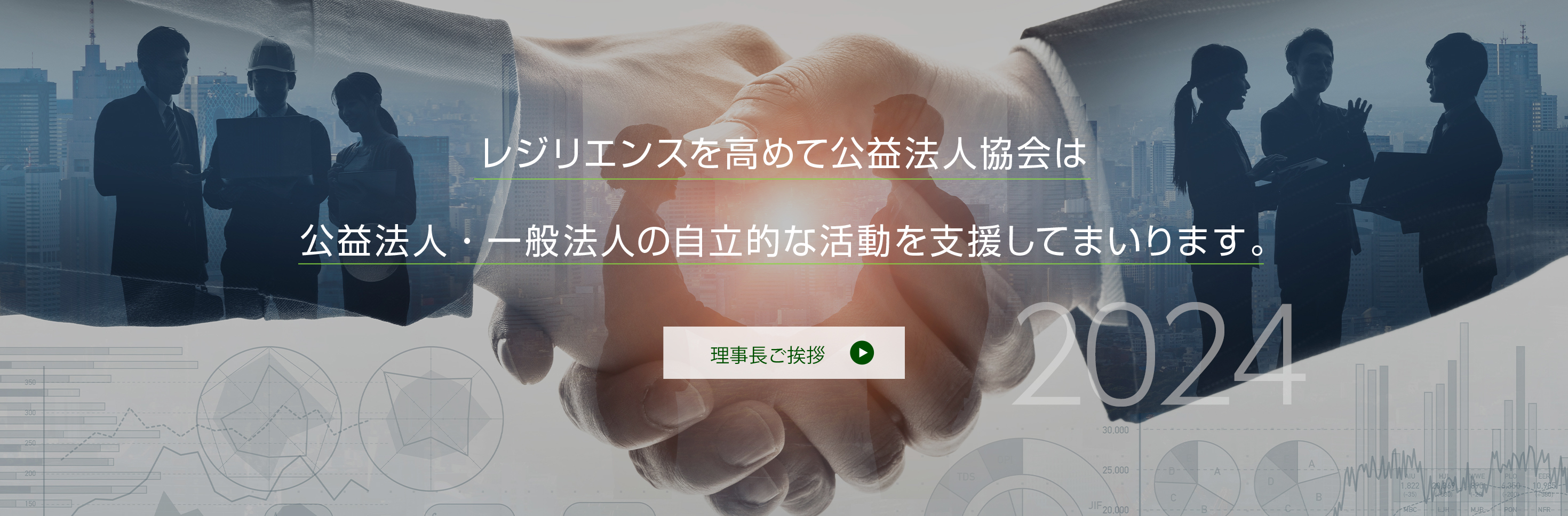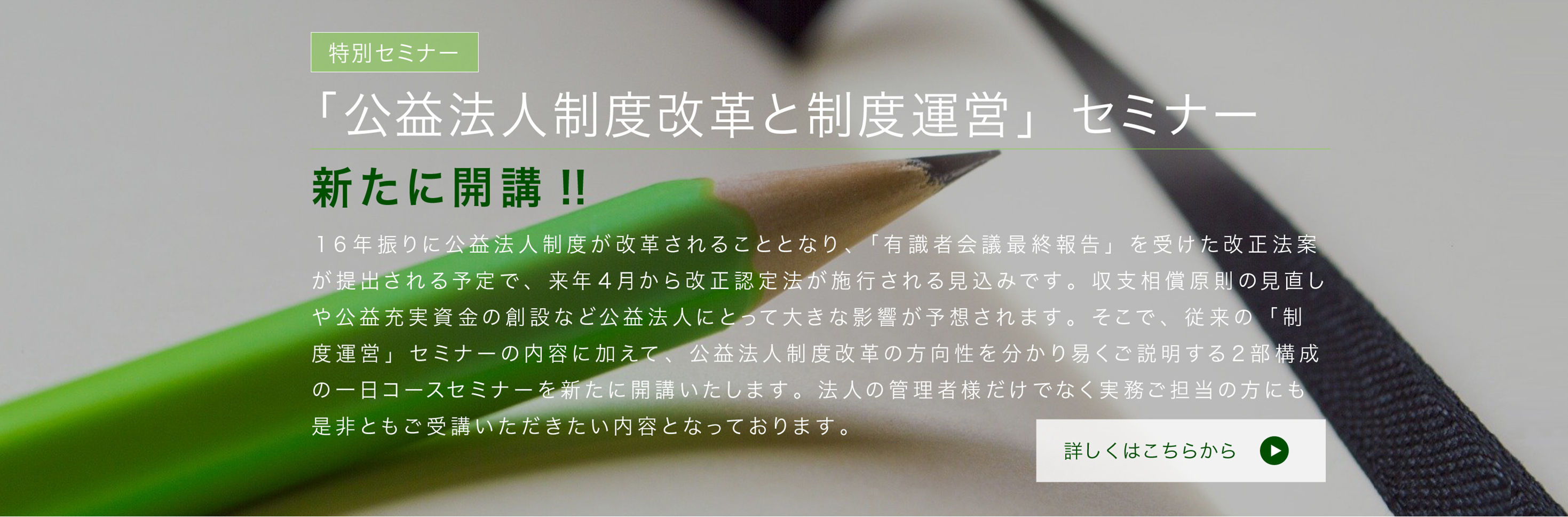新着情報
新着情報
-
2024.04.16
初開講!!オンデマンドセミナー人事労務「育児・介護休業法の改正ポイントと手続き編」募集開始のご案内
-
2024.04.5
オンデマンドセミナー(再配信)公益法人・一般法人の税務「法人税申告実務編」募集開始のご案内
-
2024.04.5
オンデマンドセミナー(再配信)公益法人・一般法人会計「決算編」募集開始のご案内
-
2024.04.5
2024年度社会福祉法人会計セミナー「基本編」募集開始のご案内(東京、大阪、名古屋、仙台、広島、高松、福岡、鹿児島)
-
2024.04.5
2024年度社会福祉法人役員・管理者向け「目からウロコの会計と決算書の見方」セミナー募集開始のご案内(東京、大阪、名古屋、仙台、福岡)
-
2024.04.4
オンラインセミナー(Zoom)「管理者のための立入検査のポイントと対策」募集開始のご案内
 政策提言/政府等のうごき
政策提言/政府等のうごき
-
2024.04.4
公益二法案、参議院内閣委員会で可決(4/4)
-
2024.03.5
公益法人制度・公益信託制度改革について、法案が閣議決定(3/5)
-
2024.01.29
商業登記規則等の一部改正に対する意見募集(パブリック・コメント)へ、意見提出
-
2024.01.17
内閣府・令和6年能登半島地震に伴う対応について
-
2024.01.11
新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議フォローアップ会合資料に対する意見募集(パブリック・コメント)へ、意見提出
-
2023.12.27
公益法人協会シンポジウム2023大会声明(12/26)